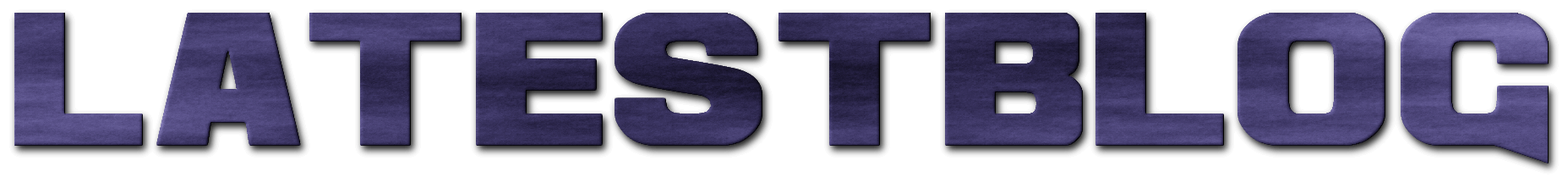「軍艦島からなぜ人がいなくなったの?」と気になったことはありませんか?。
かつてないほどの繁栄を遂げた島が無人島となった背景には、多くの人が知らない事実が隠されています。
この記事では、軍艦島に人がいなくなった理由の真相を、その独特な軍艦島の歴史や、なぜ軍艦島と呼ばれているのか?という由来と共に、分かりやすくご紹介していきます。
【この記事の内容】
・なぜ「軍艦島」と呼ばれるようになったかがわかる
・世界一の人口密度を誇った時代の暮らしぶりがわかる
・現在の軍艦島の姿と見学方法がわかる
軍艦島に人がいなくなった理由を分かりやすく解説

なぜ軍艦島と呼ばれているのか?
世界一の人口密度で反映していた時期
石炭産業の衰退と閉山への経緯
安全に採炭できる石炭の枯渇
炭鉱の島だった軍艦島の歴史
軍艦島の正式名称は「端島(はしま)」です。
長崎港から南西約19kmの海上に位置するこの島は、江戸時代後期の1810年頃に石炭が発見されたことから、その歴史が始まります。
発見当初は、漁業の傍らで小規模な採掘が行われる程度でした。しかし、日本の近代化が急速に進む中、石炭の需要は飛躍的に高まっていきます。
大きな転機となったのが、1890年(明治23年)の三菱社による島の買収です。
これを機に、本格的な海底炭鉱としての開発が始まり、日本の基幹産業を支えるための大規模な操業が開始されました。
出炭量の増加に伴い、労働者とその家族が次々と移住し、人口も急増します。最盛期には5,000人以上がこの小さな島で生活を送ることになりました。
島内には鉱員住宅はもちろん、小中学校や病院、映画館、店舗、神社仏閣などが次々と建設されていきました。
特に1916年(大正5年)には、日本で最初の鉄筋コンクリート造高層集合住宅である30号棟が建設され、その後の高層化の先駆けとなります。
こうして島全体が一つのコンパクトな都市として機能するまでになりました。
軍艦島の歴史年表
| 年代 | 出来事 |
|---|---|
| 1810年(文化7年) | 端島で石炭が発見される |
| 1890年(明治23年) | 三菱社が島を買収し、本格的な操業を開始 |
| 1916年(大正5年) | 日本初の鉄筋コンクリート造高層アパート(30号棟)が完成 |
| 1960年(昭和35年) | 人口が5,267人に達し、史上最高を記録 |
| 1974年(昭和49年) | 1月15日に炭鉱が閉山。4月20日に全島民が退去し無人島となる |
| 2015年(平成27年) | 「明治日本の産業革命遺産」の一つとして世界文化遺産に登録 |
日本の近代化をエネルギー供給の面から力強く支える重要な役割を担った軍艦島ですが、やがて訪れるエネルギー革命の大きな波と共に、その歴史的な役割を終える時がやってきます。
なぜ軍艦島と呼ばれているのか?という由来
「軍艦島」という印象的な通称は、その独特な外観に由来します。
島の周りを高い護岸堤防で囲まれ、狭い土地に鉄筋コンクリートの高層アパートが林立するそのシルエットが、当時長崎の造船所で建造中だった日本海軍の戦艦「土佐」に酷似していたことから、大正時代頃に新聞報道などを通じて「軍艦島」と呼ばれるようになりました。
もともとは南北約320m、東西約120mほどの小さな岩礁に過ぎませんでしたが、採掘規模の拡大と人口増加に対応するため、1897年から1931年にかけて6回にわたる大規模な埋め立て工事が行われました。
その結果、面積は元の約3倍にまで拡張されたのです。
限られた土地に多くの人々が住むためには、建物を上へ上へと高層化するしかありませんでした。
この垂直方向への発展が、結果として他に類を見ない異様な景観を生み出し、「軍艦島」という名を不動のものにしたのです。
豆知識:軍艦「土佐」とは?
軍艦島の由来となった戦艦「土佐」は、長崎の三菱造船所で建造された八八艦隊計画の巨大戦艦です。
しかし、1922年のワシントン海軍軍縮条約により建造が中止となり、完成することなく実験用の標的艦としてその生涯を終えました。
幻の戦艦の面影が、海の上の炭鉱都市のシルエットに重ねられたという事実は、非常に興味深い歴史の一片と言えるでしょう。
世界一の人口密度で反映していた時期
軍艦島が最も繁栄したのは、第二次世界大戦後の復興期から1960年代にかけてです。
特に1960年(昭和35年)の国勢調査では、島の人口が5,267人に達しました。
島の面積が約0.063平方kmしかないため、その人口密度は1平方kmあたり約83,600人となり、当時の東京23区の約9倍にもおよびました。
これは驚異的な数値であり、当時の世界一を記録したと言われています。
これほどまでに人口が密集した理由は、戦後の石炭増産政策のもと、全国から多くの炭鉱労働者が集まったためです。
島内には、過酷な労働を支え、家族が不自由なく暮らすためのあらゆる施設が揃っていました。
島にあった主な施設
端島小中学校(1階から7階建ての校舎)
端島病院(外科や分娩設備も完備した総合病院)
映画館「昭和館」、パチンコホール、雀荘などの娯楽施設
スーパーマーケット、商店、理髪店、郵便局
寺院「泉福寺」、端島神社
島民の生活は、物理的には狭い空間でしたが、非常に近代的でコミュニティの絆も強く、本土の都市と変わらない、あるいはそれ以上に豊かな暮らしだったと元島民は語ります。
高い給与も相まって、テレビや洗濯機、冷蔵庫といった「三種の神器」が本土の家庭よりも早く普及するなど、島全体が活気に満ち溢れた時代でした。
石炭産業の衰退と閉山への経緯
繁栄を極めた軍艦島ですが、1960年代に入ると国のエネルギー政策の転換という、抗うことのできない大きな時代の変化に直面します。
主要エネルギーが石炭から安価で扱いやすい石油へと移行する「エネルギー革命」が本格化し、日本の石炭産業は構造的な不況に陥りました。
全国の炭鉱が、政府の「スクラップ・アンド・ビルド」政策のもとで次々と閉山に追い込まれていきました。
軍艦島も例外ではなく、高品質な原料炭の需要はあったものの、石炭産業全体の斜陽化の影響は避けられませんでした。
さらに、追い打ちをかけるように1964年、坑内でガス突出による火災事故が発生。
これにより採掘の中心部が水没するという大きな打撃を受け、炭鉱の規模は縮小を余儀なくされました。
もちろん、会社側もすぐに閉山を決断したわけではありません。
1965年には新しい坑道(三ツ瀬区域)を開発して生産の維持を図り、一時的に生産量は持ち直します。
しかし、時代の大きな流れに逆らうことはできず、炭鉱事業の継続は年々困難な状況へと追い込まれていったのです。
よくある誤解:「エネルギー政策転換」だけが理由ではない
軍艦島の閉山理由は、単に「国のエネルギー政策の転換のあおりを受けたから」と語られがちですが、実はそれが直接的な原因の全てではありません。
次で解説する「採炭可能な石炭の枯渇」という、より根本的で物理的な問題が閉山を決定づけました。
安全に採炭できる石炭の枯渇
軍艦島の閉山を最終的に決定づけた最も重要な理由は、「安全にかつ経済的に採炭し得る良質な石炭が枯渇したこと」です。
一般的な燃料用の石炭とは異なり、軍艦島で産出される石炭は、製鉄に不可欠なコークスの原料となる高品位な「強粘結炭」でした。
これは石油とは直接競合しない、非常に価値の高いブランド品でした。
そのため、他の多くの炭鉱が海外からの安価な石炭との価格競争で赤字に苦しむ中でも、軍艦島デジタルミュージアムの解説によると、端島炭鉱は最後まで黒字経営を続けていたとされています。
真の問題は、採掘場所がどんどん深くなり、海面下1,000mを超える深部での作業が、技術的にも安全面でも限界に近づいていたことでした。
坑内の温度は30℃、湿度は95%に達し、ガス爆発の危険性と常に隣り合わせの過酷な環境でした。
有望な新しい採掘区域を見つけるための海底調査も行われましたが、新たな可採炭層は発見できず、これ以上の採炭は危険かつ非効率であると判断されました。
つまり、採るべき石炭を全て採り尽くし、「鉱命が尽きた」というのが実情だったのです。
閉山が軍艦島に人がいなくなった理由の真相

無人島となってからの歴史
明治日本の産業革命遺産として世界遺産へ
現在は軍艦島ツアーで見学可能
閉山決定による全島民の退去
前述の通り、安全に採掘できる石炭がなくなったという物理的な限界を受け、三菱は労働組合と閉山に向けた協議を重ねました。
その結果、1974年(昭和49年)1月15日、組合員全員の同意のもと、端島炭鉱は80年以上にわたる歴史に幕を閉じました。
炭鉱以外の産業が存在しない軍艦島では、閉山はすなわち島の都市機能全ての停止を意味します。
会社からの退去要請を受け、当時島に残っていた約2,000人の住民は、新天地での生活を求めて島を離れることを余儀なくされました。
同年4月20日の最終連絡船をもって、全島民が島を退去し、あれほどまでに賑わった軍艦島は、一夜にして無人島となったのです。
これが、軍艦島に人がいなくなった理由の直接的な答えです。
国のエネルギー政策という外的要因だけでなく、資源を採り尽くしたという内的要因が重なり、労使双方が納得の上で迎えた閉山だったという点が、軍艦島の歴史における重要なポイントと言えるでしょう。
無人島となってからの歴史
人々が去った後、軍艦島は急速に自然へと還り始めました。厳しい潮風や強力な台風に絶えず晒され、かつて最新鋭を誇った近代的な高層アパート群は、コンクリートが剥がれ落ち、鉄筋が剥き出しになり、少しずつ廃墟へと姿を変えていきます。
島は所有者である三菱マテリアルによって長らく立ち入りが禁止され、「忘れられた海上都市」として静かな時を過ごしていました。
しかし、2000年代に入ると、その荒廃しつつも荘厳な景観が「廃墟ブーム」の中で注目を集めるようになります。
写真集の出版や、映画・ミュージックビデオのロケ地として使用されたことで、再び多くの人々の知るところとなりました。
同時に、日本の近代化を支えた産業遺産としての歴史的価値が見直される動きが活発化し、保存と活用を求める声が元島民を中心に高まっていきました。
明治日本の産業革命遺産として世界遺産へ
産業遺産としての価値が再評価される中、国際的な舞台で大きな転機が訪れます。
2015年(平成27年)7月、軍艦島(端島炭坑)は「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」の構成資産の一つとして、ユネスコの世界文化遺産に登録されました。(出典:明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業 公式サイト)
世界遺産の対象は?
誤解されがちですが、島全体の建物が世界遺産なのではありません。
世界遺産の核心部分(コアゾーン)として登録されているのは、主に明治時代に建設された護岸の一部や、海底にある旧坑道などです。
島に現存する高層アパート群の多くは、その遺産を保護するための緩衝地帯(バッファゾーン)に含まれています。
この登録により、軍艦島は単なる廃墟ではなく、非西洋地域で初めて産業化を成し遂げた日本の歴史を物語る、世界的に重要な遺産としてその価値が認められることになりました。
現在、所有者である長崎市が島を管理し、崩壊の危険がある建物の保全措置や調査を進めています。
現在は軍艦島ツアーで見学可能
世界遺産登録などを経て、現在では長崎市から認可を受けた事業者が催行する上陸ツアーに参加することで、軍艦島の一部を安全に見学することが可能です。
複数の会社が長崎港などからツアー船を運航しており、専門ガイドによる詳しい解説を聞きながら、島の歴史や当時の人々の暮らしに思いを馳せることができます。
長崎市の観光公式サイトなどでも情報が提供されており、事前に予約することが推奨されます。
船上から島を周遊するクルーズと、実際に島に上陸するツアーがあります。
軍艦島ツアーの注意点
軍艦島は外海に面しているため、上陸は天候や海上の状況に大きく左右されます。
風速が秒速5m、波の高さが0.5mを超えるなど、事業者が定める基準を超えると、安全のために上陸が中止される場合があります。
ツアーを予約する際は、上陸できなかった場合の返金ポリシーや代替プランなどを事前に確認しておくことをお勧めします。ま
た、島内の見学エリアは建物の崩壊リスクを考慮して、安全が確保された南側の見学通路と広場のごく一部に限られています。
それでも、間近で見る廃墟群の迫力は圧倒的です。日本の近代化を支えたエネルギーと、そこに生きた人々の営みの痕跡を肌で感じられる、貴重な体験となることは間違いないでしょう。
まとめ:軍艦島に人がいなくなった理由

この記事では、軍艦島に人がいなくなった理由とその歴史的背景について解説しました。
記事のまとめになります。
・閉山は国のエネルギー政策転換だけでなく、安全な石炭の枯渇が最大の要因・閉山は会社と労働組合の合意の上で、1974年1月15日に決定された・1974年4月20日までに全島民が島を去り、無人島になった
「軍艦島に人がいなくなった理由」と聞いて、多くの人が国のエネルギー政策が石炭から石油へと転換したことだけを思い浮かべるかもしれません。
確かにそれは、島の運命を左右した大きな歴史の流れの一つでした。しかし、それだけが全ての答えではありません。
かつてこの島は、東京の9倍ともいわれた世界一の人口密度を誇り、最先端の集合住宅が建ち並ぶ活気に満ちた海上都市でした。その繁栄は、豊富な海底資源によって支えられていたのです。
繁栄期の豊かな暮らしぶりから、全島民が島を去り無人島となるまでの劇的な変化。
その背景には、エネルギー革命という外的要因に加え、資源を採り尽くしたという内的要因が深く関わっていました。
このように、「軍艦島に人がいなくなった理由」は、複数の要因が複雑に絡み合った結果なのです